ハングルの「三国誌」の話
三国志を好きになりはじめたばかりのある日のこと。
ふと図書館で「三国史記」なる本を見つけ、すわ三国志だと思って手に取ってみたら、三国は三国でもそれは朝鮮の三国史(新羅・高句麗・百済)だった――
という哀しき過去を我々は誰しもが抱えているわけですが、ついこの前、そんな昔の傷を思い出させる体験をしました。
それはうちの図書館の地下書庫でのこと、ハングル書架に並んでいたその本は『大三國誌』という題名で、「三国誌」と「後三国誌」それぞれ五巻から構成される全十巻の本でした。
著者は――あとで検索して分かったことですが――金龍済(三国誌担当)と趙誠出(後三国誌担当)という人で、1979年にソウルの平凡社(あの平凡社?)から刊行されたものだそうです。
その本を初めて見たとき、もちろん僕は「おっ」てなりました。「三国」という文字を見たら反応するよう、我々は躾けられておりますので、これは自然な反応ですね。しかもそれは「三国誌」と「後三国誌」のセットと来た。こんなパッケージ聞いたことがない。「後三国」とは――?
けれども同時に、これで僕はなかなか手練れですので、すぐさま例の朝鮮三国史のことを油断なく思い出しました。うん、なにせここはハングル書架なのだから。当然、この場で「三国」と言ったら魏・蜀・呉でなくて、新羅・高句麗・百済なのだろうなと。
しかも三国志だけでなく、実は日本十進分類法にもささやかな自信がある僕は、そこに貼られたラベルが"221"であることに抜け目なく気づいていました。221は朝鮮史のカテゴリ。この本がもし本当に三国志ならば、その数字は222.04、もしくは923.5でなくてはならない。そう、この本は間違いなく朝鮮史の「三国誌」でした。
ただ、たとえ違うとわかっていても、書架を通りかかるたびに目はそちらの方に行ってしまうもの。
本当にまぎらわしいんだよなあと思いつつ、しかしその一方で「待てよ」とも思う。
「三国誌」はともかく、「後三国誌」は何なんだろう?
あ、やっぱりあるんだ(九世紀末)
ひょっとしたら、あの 「後三国志」のことかもと思ったのだけれど(落胆)
そうか、違うのか。
びっくりしました。
いくぶんかの葛藤のすえ、その『後三国誌』を実際に開いてみたら、これ本当に『三国志後伝』のハングル訳だったんです。目次を見てわかりました*1。
つまりこの『大三国誌』なるものは本当に本物のまぎれもない「三国志」で、『三国志演義』と『三国志後伝』をセットとして現代韓国語に訳し、ひとつのシリーズにしたものだったんです。ラベル間違ってるじゃねえか。
これはちょっとおもしろいです。
『三国志後伝』が『三国志演義』の"続編"であることは、『後伝』サイドが『三国志演義』人気にあやかって勝手にそう自称しただけのことです。そこで描かれる五胡十六国時代の争乱は本来的には『三国志演義』の物語と直接関係しません。だから両作品をあたかも一対のように扱うのは間違いと言えば間違いなのですが、でも、すごくわくわくする。
それに、――たとえ前半の「三国誌」こと『三国志演義』のおまけであろうとも――1970年代に『三国志後伝』を世に出したことにも惹かれます。日本でさえ、100年くらい前に『通俗続三国志』『通俗続後三国志』(江戸時代の『三国志後伝』の翻訳)を復刻したっきりなんですから。よく知っていたなあ。
と、いう小さな発見をしたのが半月前のこと。
その後も折にふれてパラパラ眺めていたのですが(本当に眺めるだけ。ハングルわかんないから)、もちろん手に取るのは『後三国誌』のほう。『三国誌』のほうは、別に韓国語訳の『三国志演義』とか珍しくもなんともないと思ったので。
それが昨日になって、ふと『三国誌』を開こうと思ったのは、さてどうしてでしたっけ?
間違えて手に取った?
ラベルを直そうとした?
ひょっとしたら、底本が何なのかと(李卓吾本?毛宗崗本?)、多少は学術的なことで気が向いたのかもしれません。でも思い出せません。大した関心があって手にしたわけではないのは確かです。
だからこそ、それは本当に出し抜けで、心底驚きました。
これ『三国志演義』じゃなかった。
李卓吾本とか毛宗崗本とかそういうのじゃなくて、『三国志演義』でさえなくて、

つまりこの本は『三国志演義』&『三国志後伝』の翻訳と称してはいるものの実態は、前半は吉川英治『三国志』、後半は江戸期の和訳本『通俗続三国志』『通俗続後三国志』で、これらをセットに韓国語訳して『大三国誌』って銘打った本だったんです。なんで?そんなキメラ的なことに?
まず、原書を見れない『三国志後伝』の事情はともかく、どうして『三国志演義』の方までわざわざ原書じゃなくて日本語から重訳してしまったのか。
百歩譲って、なにか理由があって中国語より日本語のテキストを使う方が楽だったとして*2、でも、なんでよりによって『吉川三国志』を選んじゃったのか。
この頃なら立間祥介訳だって小川環樹訳だって、ちゃんとした『三国志演義』の現代日本語訳はもうすでにあったのに、なんでよりによって『三国志演義』じゃない『吉川三国志』を選んじゃったのか。
ひょっとしたら、彼らは本気で、『吉川三国志』を『三国志演義』の忠実な翻訳だと勘違いしていたのかもしれません。
この本には、表紙、奥付、序文のどこを見ても「吉川英治(요시카와 에이지)」の名前はありませんでした(たぶん)。その意味で、この本は無許諾で翻訳した海賊版とも言えてしまうかもしれません。
でも、もし彼らが本当に『吉川三国志』を『演義』の全訳だと信じ、そして自分たちの仕事を「『吉川三国志』という既存の翻訳を参考にした『演義』の翻訳(重訳)」と信じて疑わなかったとしたら、その場合『吉川三国志』は底本・原書ではなくあくまで参考文献扱いで、必ずしもクレジットしなくても不思議ではない、のかなあ。
なにか『横光三国志』を思い出させる話ですね。
あれも『吉川三国志』を事実上の原作にしながら、おそらく公式では今に至るまでまったく吉川英治の名前を出しておらず、かと言ってそのことで何か怒られたということも聞きません。
あと柴田錬三郎の『三国志』。これも表向き『三国志演義』の翻案を装ってますけど、中身は完全に『吉川三国志』のダイジェストです。吉川英治の名前はもちろんクレジットしていない。柴錬はこの後、これをもっとちゃんと『演義』に寄せて、そしてオリジナリティを盛り込んだ『英雄ここにあり』を発表しますが、でもところどころに『吉川三国志』だった頃の名残が見られます。柴錬はこれで吉川英治文学賞を受賞しました。
どうも、『吉川三国志』は"こういう"使い方をされてもなんかセーフだったんじゃないか、という印象は前々からありました。もうちょっと言うと、あまり、いっこのオリジナル作品とは見なされていなかったのではないか、と。
立間先生が日本ではじめて『演義』の現代語訳を出版した時、「お前の翻訳は吉川英治のと違って全然面白くない。吉川のようにもっと原典に忠実にやれ」と読者に叱られたエピソードは有名です。
なにより吉川自身が、自作を「全訳」「全意訳」と呼ぶ向きがありました。
連載初期、まだオリジナリティにあふれていた頃には自作を「わたくし流」と称していた吉川は、やがて中盤以降ほとんど創作を盛り込めなくなり、ただ『演義』(『通俗三国志』)を書き写すばかりになってしまうと、それを自覚してか「全訳」などとトーンダウンしていったのです。
今ではもちろん『吉川三国志』≠『演義』であることは常識ですけど、かつての読者たちにとってはおそらくそれはそうではなかった。
僕の知る限り、それが普通に言われるようになったのは――『吉川三国志』の読者がちゃんとそれを説明されるようになったのは、吉川英治が死んだずっとずっと後、たぶん1979年が初めてだと思います*3。柴田錬三郎や横山光輝の『三国志』よりも後、くだんの『大三國誌』が刊行されたちょうどその年のことです。
もっとも柴田錬三郎にしろ横山光輝にしろ『大三國誌』にしろ、彼らは一般読者ではなく出版する側のプロなので、そんな単純な混同をするかなという疑問もあります。『演義』と『吉川三国志』、両方を見比べたら違いは一目瞭然なんだから。慶応で中国文学やった柴田錬三郎がまさか『三国志演義』を見たことないってこともないはずです。
だからひょっとしたら、そもそも「翻訳」に対する感覚が今と違ったのかもしれません。
吉川自身が「翻訳」「意訳」と言っていたように、『演義』と『吉川三国志』の相違程度だったら、ゆるやかな意味での「翻訳」の範疇だったのかも。いっこの一時創作でなく、古典小説の「翻訳」だから、ダイジェストとか漫画化とか重訳とかくらいだったらタダ乗りしても(当時の出版常識では)あまり問題視されなかった、のかも。
想像ですけどね。
翻訳、翻訳ってなんなんでしょうか。
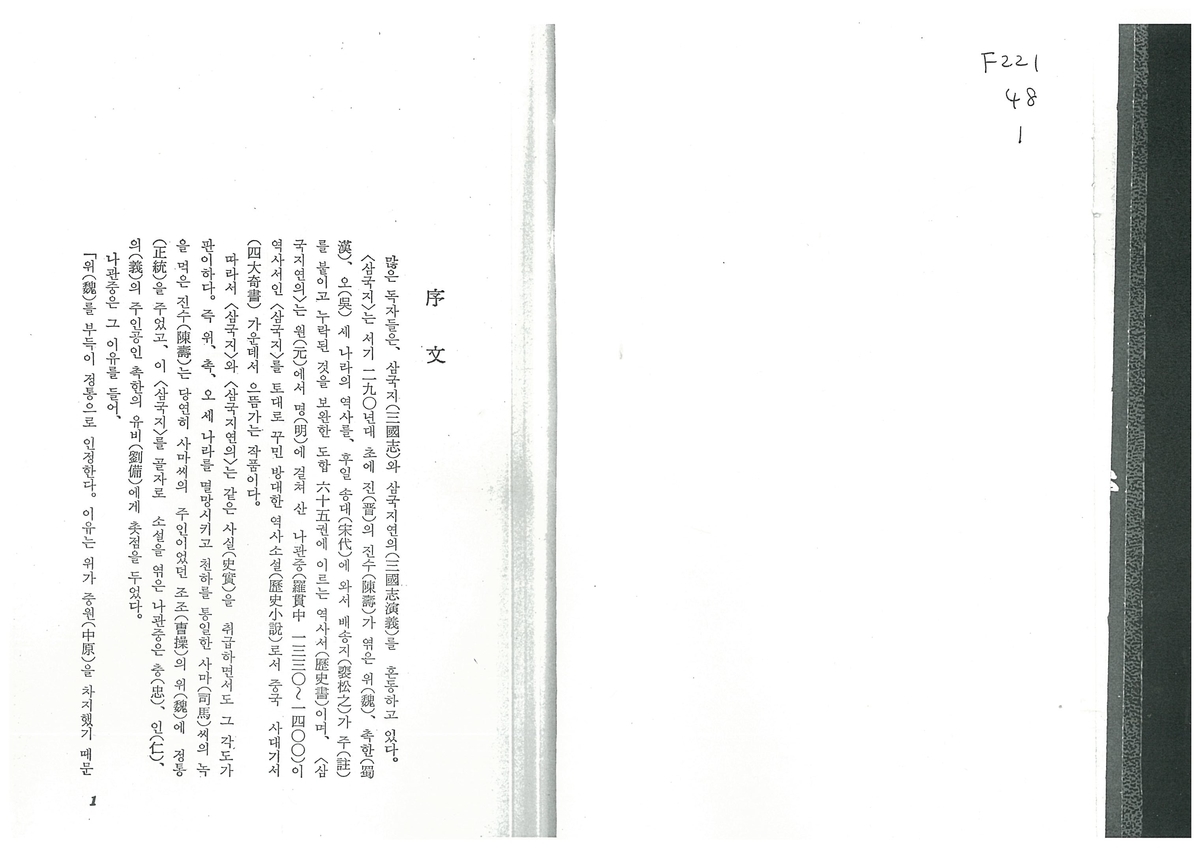
『三國誌』の序文(1/3)。右上は本書の請求記号。だが正しくは221(韓国史)ではなく、222.04(中国古代史)でも923.5(中国近世小説)でもなく、913.6(日本近代小説)だった
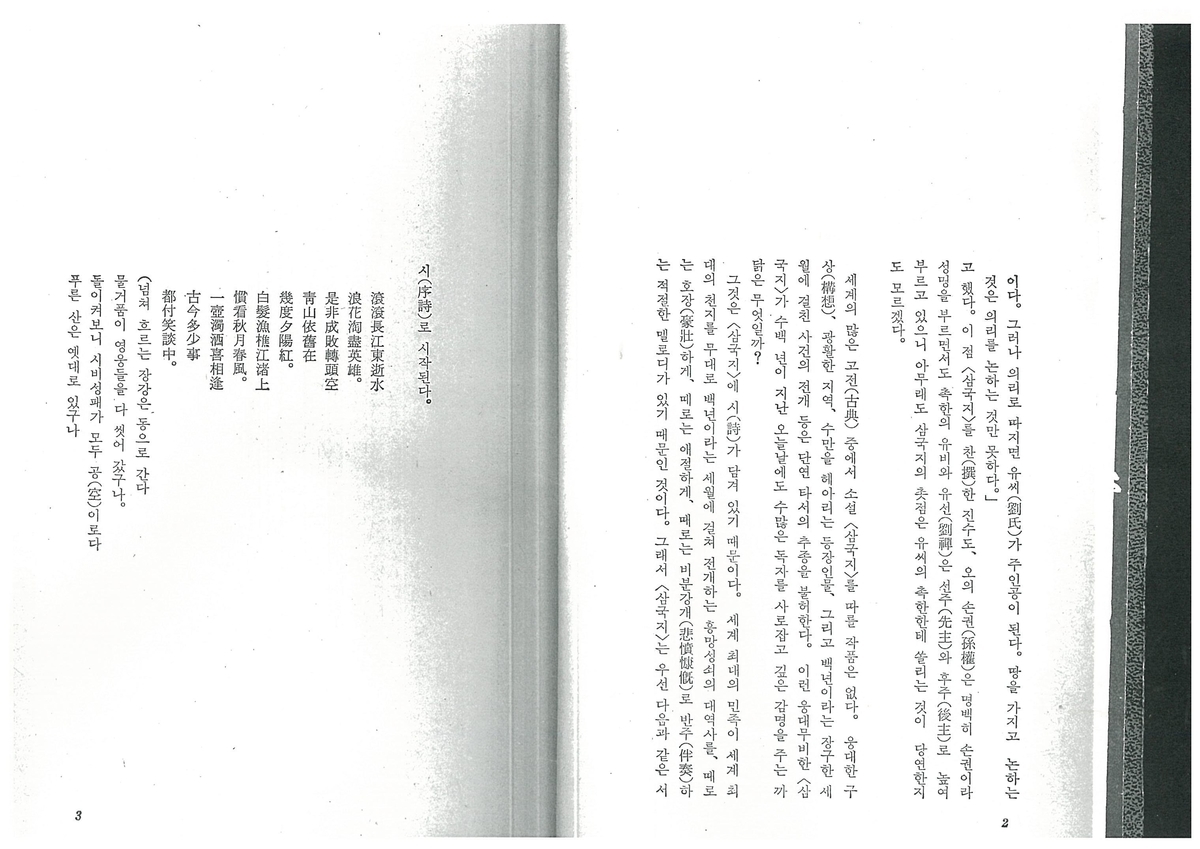

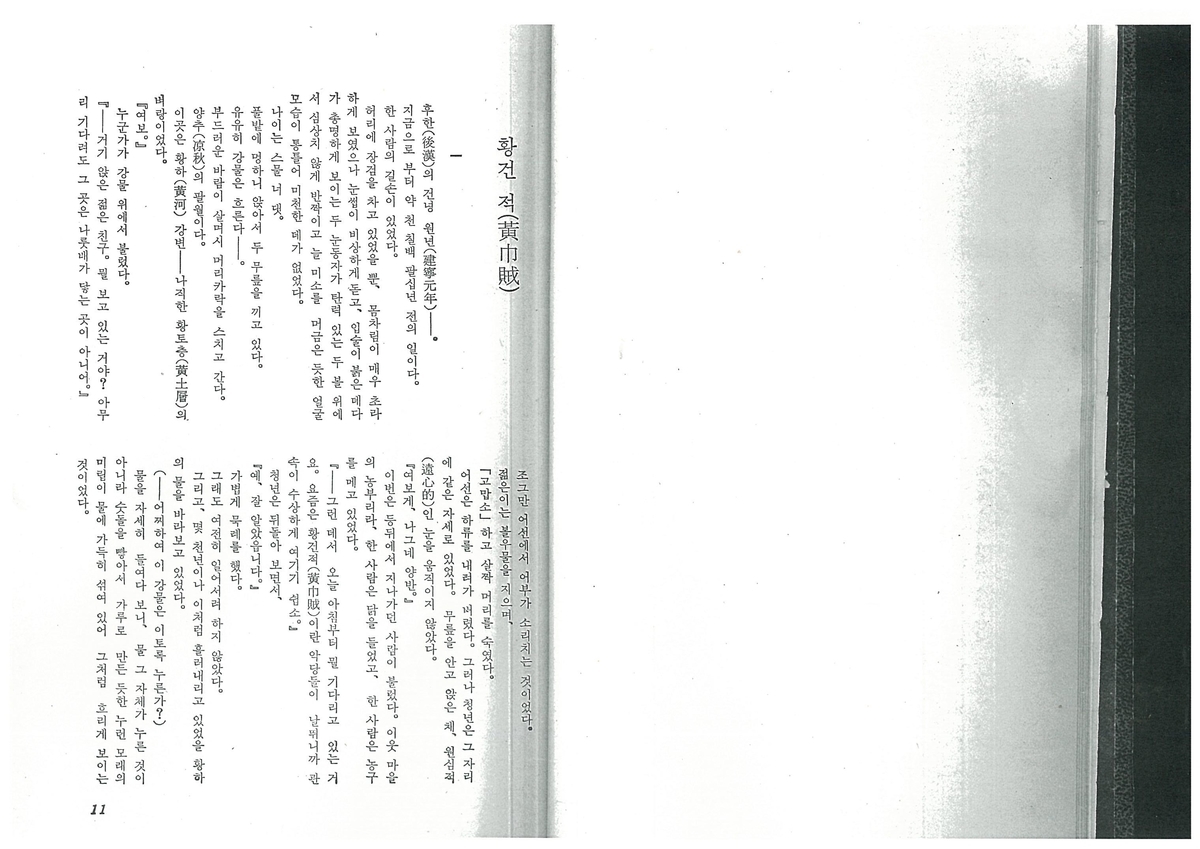

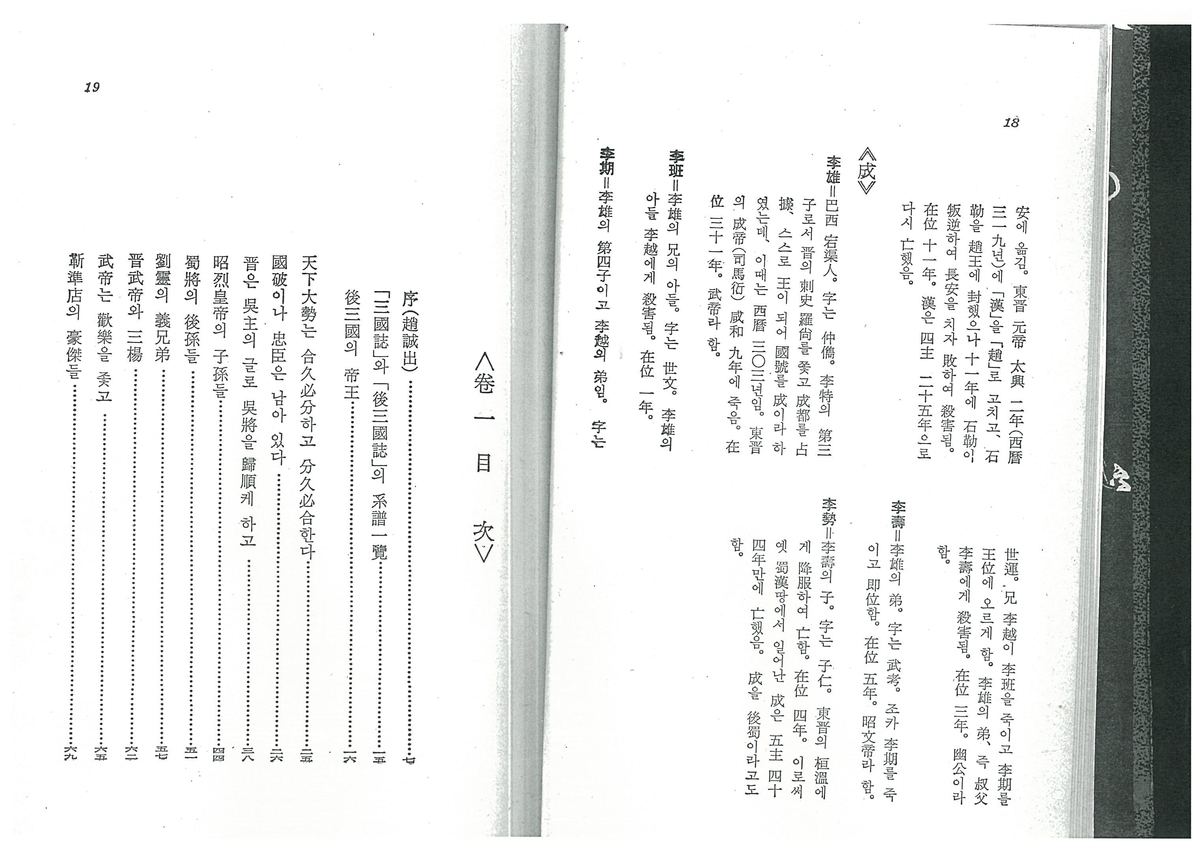
*1:正確には、『三国志後伝』の和訳である『通俗続三国志』と『通俗続後三国志』からの重訳でした。『通俗続三国志』は『三国志後伝』の翻訳でありながらちょっと構成が違うので、目次を見ればどっちに拠ったか見当がつきます。それに本書の序文にも、『通俗続三国志』に拠った旨が書かれてました。『大三国誌』が出版された70年代では、『三国志後伝』の原文を見ることはほとんど不可能でした。
*2:『三國誌』の訳者の金龍済という人は詳細不明ですが、あるいは戦前日本のプロレタリア文学で名を馳せたという作家金龍済と同一人物かもしれません。
*3:これは『決定版 吉川英治全集』が刊行されたときのことです。このとき初めて、『吉川三国志』にちゃんとした解題がつけられました。担当は、上述の立間祥介先生でした。
全訳出来!(予定)
こんにちは。
ここ最近、のっぴきならない理由で、汲古書院のホームページをちらちら覗いてはそわそわする日々を送っていたのですが、そこでついさっき、思わず声を上げてしまうくらいびっくりなことを見っけました。ほんとに「おぅわっ」って声が出ました(そしてそれはバイトの休憩中でした)。
| 書名 | 詳注全訳水滸伝 第一巻 |
|---|---|
| 概要 | ◎原文の味わいをいかに伝えるか。渾身の『水滸伝』訳注書発刊! |
| ジャンル | 中国古典(文学) 中国古典(文学) > 唐宋元 中国古典(文学) > 明清 |
| 著者 | 小松 謙 訳 |
ちょっとびっくりすぎて言葉がうまく出ません。
そわそわの原因だった『全譯三國志 魏書(一)』刊行決定が一瞬霧散してしまったくらいです。いやこっちだって負けないくらいの渾身のつもりではあるのですけど。そう、そういう次第で、僕が参加した本がそのうち出るのです。すごく嬉しいです。よろしくお願いします。
いや、しかし、それはそれとして、小松謙先生による『水滸伝』の全訳、それが「詳注」を堂々と看板に掲げ、しかも金聖歎の批評まで全て訳しているというこのインパクトたるや。
とうとうこんな本が出るんだ、とファンとしてはにわかには信じられない想いです。
まさしく小松先生が言うように、こうした作品は古典的小説として長年きわめて深く重んじられてきた一方で、「厳密な校訂を加え、詳細な注釈を加える」ような"本気で読まれる"機会には恵まれてきませんでした。
それは、「所詮は白話文学」という意識が根強くあったことも一因なのでしょうが、ただそれ以上に、「白話小説だからこそ手ごわく、容易に手が出せない」という畏敬の念があったからではとも僕は想像しています。
白話小説は、それが市井の文芸であるがゆえに、それを生んだ時代と社会の常識、風俗、通念、慣習、言葉、流行を知らないことには――記録に残りづらく現在では把握困難なそれらを知らないことには――決して本当の意味での理解はできないのです(と偉い専門家の人が言っていました)。
その意味で、白話小説を読み切ることは、経書やいわゆる「文学」を読むことに匹敵する大仕事……いや後述のハンデも加味するとそれ以上に険しい道のりなのかもしれません(と僕は想像しています)。
『水滸伝』には、吉川幸次郎訳や駒田信二訳などの名訳と謳われるものがすでに存在します。
けど、たとえこれらの名訳を以てしても、僕たちのような一般層が『水滸伝』を読むのは、「ほとんど不可能」と「ものすごく困難」の中間、それも限りなく後者に近い。
さっき書いたことのと同じく、作品の背景にある時代の文化と価値観がわからないので、人物の心情とか、編者の表現の意図とか、出来事の理非とか、そういう機微を理解することができず、本当の意味での読むこと(理解すること)ができないのです。もちろん、できないことはできないと割り切って、自分の感性を恃みに作品を味わうという手もないでもないのですが、でもそれは作品を「理解すること」とはまた別の受容スタイルです。古典て、すっごく読むのが難しいのです。
なので、僕らはただ待つことしかできませんでした。
「原文の雰囲気を可能な限り移した自然な日本語訳」と「原文のすべての箇所に対する解釈を明示した詳細な注釈」がセットになった訳注――それは最前線の研究者をしても相当に困難なことだと聞きました――が奇跡的に現れるのを、ただ待つことの他にないのです。
ね、人前で叫び声をあげてしまうのもやむなし、と思いませんか?(思いますね?)(思いましたね?)
前に、専門家の先生がふと漏らしたのを聞いたのですけど、白話小説研究というものはようやく最近になって本格的に始まったばかりの、それこそ千年の蓄積がある経学に比べたら、本当にこれからの若い学問なんだそうです。
テキストの整理がようやくそれなりに目途がついて、ようやく読みが始められるようになったばかりの分野。
なので、「ついにこんな本が!」と思うと同時に、それ以上に「もうこんな本が!」という気持ちがより強いです。
すごいですねぇ、本当に。しかも著名な白話小説ではとくに難しいと聞く『水滸伝』で。
ただ……
こういうが刊行されるのを見てしまうと知ってしまうと、どうしても望蜀の想いが湧き上がってしまうわけで。
なので、ぜひ、いつか、『三国志演義』でこういう本を。
講演会「父・吉川英治と三国志」
最近自分の宣伝ばかりですけど、今日はちょっとまじめな宣伝をさせてください。
来週、9/14(土)の三国志学会で、吉川英治のご長男の英明さんに「父・吉川英治と三国志」というテーマでご講演していただくのです。
英明さんは英治没後から長らく、全集の刊行責任や吉川英治記念館館長を務められてきた人です。もちろん私人としての英治を一番よく知るおひとりでもあります。
『吉川三国志』ファンの僕としては、一度でいいからお話聞けないかな、お会いできないかな……なんて思ったことすらありませんでした。全然。そのくらい遠い存在でした。まさかオファーを出す機会があろうとは、まさかOKをもらえるとは。
全国の『吉川三国志』ファンはぜひ14日、ぜひ三国志学会にいらしてください。吉川作品のこと、当時の思い出など、貴重なお話が聴けると思います。
詳しいことはこちらの公式ページにありますので。
とは言っても、学会ってどういうものかよくわからないし、正直得体が知れないって思われてるかもしれません。毎年、「三国志学会に興味はあるけど敷居が高い」ってツイートなんかもけっこう見かけます。たしかに学会って基本的には内輪のもので、外部の人や研究者でない人が来ることはあんまりないですしね。
でも三国志学会はそのへんがだいぶヘンな学会で、たぶん会員のだいたい6割か7割が三国志ファンの一般人です。研究者のほうが少なくて、それでその研究者もだいたいはやっぱり三国志ファンです。三国志に興味があるなら誰でも参加してほしい、ってコンセプトで作られた学会なので、そういう風になりました。学会終わった後の懇親会なんかも、三国志ファンのオフ会の場みたいな空気になってます。ようはちょっとヘンな学会なんです。
なのでもし興味があるなら、ぜひ気軽に来てください。
学会当日も、参加者に特別なにかしてもらうことはないです。発表者の話を聞くだけです。
事前申込もないです。飛び入りで来てください。参加者はだいたい例年100人弱くらいかな。途中から来ても途中で帰っても大丈夫です。
非会員でももちろん参加できます。参加費は500円ですが、英明さんの講演から聞くならタダです。懇親会は参加自由です。こっちはお金かかります。
こんな感じの会ですね。
とにかく『吉川三国志』が好きって人にたくさん来てもらえたら嬉しいです。
よかったらぜひ。
箱崎みどり『愛と欲望の三国志』
僕もこれから読むので、なにかこう気の利いた宣伝なんかはできないのだけど、
ただとてもいい本なので、どうかぜひ読んでください。

正しいなにかなんてない
しあさってから、上野の東京国立博物館で三国志展が始まりますね。
こう言ってはバチあたりなのだけど、僕が思っているよりはるかに、この展覧会は世間では大きな注目を集めているらしい。実際に見てはないけどばんばん広告出してるそうだし、書店では三国志関係の書籍や雑誌がはっきりわかるくらいに増えている。うーん、ちょっと意外だった。
しかしそのおかげで、僕もこの2ヶ月でいろんなお仕事を手伝わせてもらいました。これまでやらしてもらってきたのとおんなじくらいの仕事量を、2ヶ月間でどさっとやった感じです。ありがたいことです。どこかで見かけたらよろしくお願いします。
・『ユリイカ』2019.6月号
執筆:「新しいファンのための「三国志」案内」
・『時空旅人』2019.7月号
執筆:「日本の関帝信仰を巡る」
・渡邉義浩監修『史実としての三国志』(宝島社新書)
・『歴史探訪』Vol.4
執筆:「軍事面での曹操の評価はどうだったのか?」
どれも一所懸命にやって、とくに日本の三国志作品を好き勝手に紹介させてもらった『ユリイカ』の記事なんかは個人的にもとても楽しかったのだけど、宣伝するヒマもなく、完全にタイミングを逃がしてしまった。たぶんもうとっくに次号が並んじゃっている。残念。
ただ、このなかでひとつだけ、たぶんもう書店に出てると思うけど、『歴史探訪』に書いた日本の関帝廟の記事を宣伝させてください。なしてこれだけかと言うと、この記事がとても大きな過ちを犯しているからです。
この記事では、日本各地の関帝廟を紹介するなかで、神戸関帝廟に触れてこんな感じのことを書いた。文章は変えているけど大意はそのまま。
神戸関帝廟は、繁華街である神戸南京町とは離れた住宅地にある。中華街のど真ん中にある横浜関帝廟のイメージとは大きく違う。なぜ中華街ではないところに関帝廟があるのか。それは関帝廟の本質的な役割が、華僑の福利施設であるためである。つまり生活空間の一部なので、華僑の住む住宅地にあるのが正しい。むしろ横浜のような観光地化された関帝廟の方が珍しい。
問題は最後のふたつの文章、とくに「関帝廟は住宅地にあるのが正しい」と言っていることにある。
問題は2点。
ひとつは、関帝廟が住宅地にあることが正しいのかどうかである。ちゃんと確認してないのでわからないけど、たぶん住宅地でないところにある関帝廟もかなり多いはずだ。「生活空間の一部なので、住宅地にあって不思議はない」と書くべきである。
問題のふたつめ。よしんば、住宅地にあることが関帝廟のスタンダードだったとしても、それを「正しい」と表現することにある。道義的にはこちらの方がずっと問題は重い。
ある事例を「正しい」と評価することは、逆に言えばそうではない事例を「正しくない」と否定することと同義である。実際、この記事を読むと、関帝廟として正しいのは神戸のほう、正しくないのは横浜のほうという風に読める。少なくとも僕には。
関帝信仰のような現存する伝統文化を対象に研究する者は、研究対象に「正しい」「正しくない」と評価を下すこと、つまり特定の文化・習慣の在りようを否定することを強く強く戒める。
僕が聴いた話を具体例にしよう。
ある高名な媽祖信仰の研究者が、日本のどこかの媽祖祭りを見て、それが本場の媽祖祭祀から見て"間違っている"と思った。そこで彼はそのお祭りを"正しく"改めさせた。結果、その地域の固有の媽祖信仰のあり方が失われてしまったという。
この話が具体的にどの研究者を指しているのか、そもそも実話なのかどうかもわからない。尾ひれがついている可能性もある。一種の寓話と考えたほうがいいかもしれない。つまり、研究者が高度な専門知識を軽率に振りかざし、文化の現場を「正しくない」と否定・介入することはあってはならない。それは時として文化を致命的に損なうことになる、という教訓である。
僕もまた、文化の当事者を可能な限り尊重するのが文化研究の基本中の基本だと考える。そういう風に教えられてきた。もちろん僕は、関帝信仰の研究者じゃない。仕事をしてお金をもらったのにこう言うのも何だけど、せいぜい好事家にすぎない。しかし好事家にすぎなくても――もしくは好事家だからこそ、こういう守るべき研究精神については偉そうに振りかざしていきたいと思っている。
そのため、僕のこの記事に含まれた「正しい」という3文字の表現は、たとえそれが現実的にはほとんど影響力を持たないとしても、それでも犯してはならない大きな過ちだと思う。なんで「正しい」なんて書かれているのかわからない。憶えている限りでは、僕の手が離れた時点でこんな表現はなかった。どこかで付け足されたのか。あるいは僕の見落としもあったのか。
ただ、無責任な物言いになってしまうけど、正直その原因についてはそんなに気にしてない。僕はこの過ちを見つけた時、ただ「ブログに書くことができたな」と思った。もしこれが他の人の文章だったら、さすがにここまで強くは言えない。けれど自分の文章に対してなら遠慮なく言いたいことが言える。
文化や信仰に正しいなにかなんてない。関帝信仰に興味を持ってから僕は一貫してそう考えてきた。なので今回の記事では、関帝廟がテーマであるなかであえて黄檗宗萬福寺の関帝信仰を取り上げている。
過ちはあるけど、もし読んでもらえたら、とても幸いです。
袴田郁一/山本佳輝『マンガでわかる三国志』
ずっと続けていたはてなダイアリーがサービス終了してしまうということで、この記事からは新しく、はてなブログで書いています。慣れないなあ。
それではてなブログでの書き初めということで、思い出話から始めることをご勘弁ください。
2年ちょっとくらい前、『マンガでわかる三国志』という本を書いた。
それまでも一般書の執筆に関わらせてもらうことは何度かあったんだけど(当たり前だけど、そんな幸運は普通はない)、この本ではじめて、一冊丸ごとの文章を担当して、表紙にクレジットさせてもらえることになった(当たり前だけど、そんな幸運は全然あるものではない)。
「マンガでわかる」ってタイトルのくせに、僕の文章が7割8割も占めるという、僕にとってはめちゃくちゃに贅沢なお仕事だった。おかげで、マンガ目当てで三国志を新しく知ろうというお客さんをがっかりさせることもあったようで、それについては平謝りするしかないのだけど(本当にごめんなさい)、けれど僕にとっては本当に楽しいお仕事だった。
ひとつは、山本佳輝さんという漫画家さんと一緒に仕事ができたことが僕には楽しかった。
マンガでわかる三国志、発売! : てるピヨ。『山本佳輝のイロイロブログ』
直接やり取りすることはなかったのだけど、送られてくるネームを読ませてもらって、一目でピンときた。この人は相当な三国志オタクだと。しかも僕と同じように、絶対『蒼天航路』でハマった人だと。
ネームのあちこちに『蒼天航路』の匂いがぷんぷんだったし、曹操のキャラクターとか桃園の誓いとか呂布の最期の描き方なんてのが、「そうそう、今の日本のオタクのあいだだとそういうイメージで定着してるよな」っていうのがとても伝わってきた。同じ三国志キャリアを歩んできた人にはわかるだろう、ある種の三国志愛がひしひしと感じられた。絶対、僕と同世代かちょい上の先輩オタクだろうと確信していたし、実際、本が出たあとの山本さんのブログを見たら「無双2、蒼天航路、恋姫無双で三国志にハマった」って書いてあった。僕の勘はどんぴしゃだった。
一応、本のコンセプトに合わせて、『三国志演義』にそぐわない描写やキャラクター造形は申し訳ないけどがっつりリテイクしてもらったけど、僕個人はとても楽しく読ませていただいた。執筆者特権だ。ズルい。漫画の仕事を手伝うとプロのネームから見れるっていう役得があるのだけど、このときほどそれを感じたことはなかった。送られてきたファイルは大事に保管している。
お会いすることはなかったけど、同世代の三国志オタクとして、今でもひそかにシンパシーを感じている。
そんな山本さんのネームに触発されたってだけではないけれど、僕の文章も僕の三国志愛を前面に出してしまった。
企画段階ではこの本は、『演義』のストーリーをベースに史実の三国志を解説するという方向で提案をいただいていた。けど僕としては、そういう手の本はいくらでもあるし、ここは絶対に『三国志演義』の方をメインにした本にしたかった。
『演義』そのものに踏み込んで、そのフィクションとして創作意図や、背景になっている三国志物語の多様性を解説する本は、僕の知る限りではかなり数が限られる。
僕は三国時代の歴史学の専門家でも『三国志演義』の専門家でもないし、ましてプロのライターでもない。でもこの世代の三国志ファンとしては、正直に言ってかなり自負するところがある。三国志物語の多様性という点についてなら、プロの三国志研究者を相手にしてもちょっとは引けを取らない自信がある。
そういう人間から見た、『三国志演義』の物語としての面白さや豊かさに焦点を当てた本にできないかと、かなりワガママを通してもらってしまった。『三国志演義』は三国志をざっくりと知るだけのお手軽本でない、それ自体を深く読み込むことだってかなり楽しいんだぞって想いでひたすらに書いた。
結果、できた本は「マンガでわかる三国志」っていう初心者向けっぽいタイトルとは裏腹に、小説やマンガで三国志を熟知した人たちに向けて、三国志世界のさらなる広がりを知ってもらいたいという、だいぶマニアックな本になった。おかげで編プロの人にはかなり迷惑をかけてしまった。でも文章をたくさん直してもらったり、的確な図解を入れてもらったおかげで、自分から見てもただのわかりづらいマニアの本ではなくなった。本当に迷惑をかけてしまった。
自分で本を出すなんてこれまでもこれからもない機会だしと、ここを先途とばかりに自分のエゴが盛りだくさんの本にしてしまったけど、まわりの三国志ファンにはお世辞にしてもまあまあ褒めてもらえたし、「これは演義ファンのための本だ」「三国志にはいろいろな受容の仕方があったことがわかった」とまさに僕がやりたかったことを感想で書いてくれた人もいた。本当に、こんな幸運は全然あるものじゃない。すべて編プロや出版社の人、そして監修の渡邉義浩先生のご厚意の賜物である。
それともうひとつ、同じ池田書店の『マンガでわかる源氏物語』(砂崎良著/上原作和監修/亀小屋サト絵)もかなりおすすめです。
この本は単に『源氏物語』のおもしろさや表現の美しさを解説するだけじゃなくて、光源氏と紫式部たちが共有していた、現実の平安貴族社会の構造と常識を踏まえて作品を読み解くことにも重点を置いている。科学的な文学鑑賞という、一般書としてはけっこう学術的な攻めたアプローチをした本だと僕には思えた。
それで完全に言い訳になるけど、僕は執筆前のサンプルでもらったこの本がすごくおもしろくて、僕も『三国志演義』で同じことをしたいと、最新の『演義』研究の知見を――具体的には仙石知子先生や後藤裕也先生や竹内真彦先生たちの研究をばんばん盛り込ませてもらった。僕の本のマニアックさの責任の半分くらいはこの本にある。
なので、もし僕の本が悪くないなと思ってもらえたなら、ぜひこの本とか、ほかの「マンガでわかる」シリーズも読んでみてください。きっと僕のよりもいい本です。

マンガでわかる 源氏物語 (池田書店のマンガでわかるシリーズ)
- 作者: 砂崎良,上原作和,亀小屋サト,サイドランチ
- 出版社/メーカー: 池田書店
- 発売日: 2011/11/15
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 32回
- この商品を含むブログ (1件) を見る


